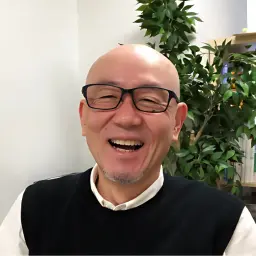
執筆者:山崎 孝
公認心理師・ブリーフセラピスト・家族相談士


「結婚が決まって嬉しいけれど、これからの生活に不安もある…」
「パートナーとは上手くいっているはずなのに、どこかモヤモヤする…」
「大切な話はなんとなく避けてしまっている…」
そんな気持ちを抱えているあなたへ。
結婚前カウンセリングは、お二人の幸せな結婚生活への第一歩を支援する場所です。日常会話では触れにくい話題もゆっくりと話し合い、お互いの理解を深めていきます。
夫婦・カップル関係に明るい公認心理師がお二人の対話をサポートすることで、漠然とした不安は具体的な準備へと変わっていくはずです。
結婚を控えた多くのカップルは、喜びと共に様々な気持ちを抱えています。
「パートナーのことは大好きなのに、なぜか不安がある」
「結婚生活のイメージがうまく描けない」
「相手の家族との関係はうまくいくだろうか」
「仕事と家庭の両立ができるだろうか」
「子どもを持つことについて、まだ話し合えていない」
これらの気持ちは自然なものです。新しい人生の節目を迎えたとき、多くの人が様々な思いを抱えるものです。大切なのは、それらの気持ちに向き合い、パートナーと共有していくことです。そのプロセスを丁寧にサポートします。
結婚前カウンセリングでは、以下のような成長を実感していただけます。
日常会話では気づかなかったお互いの価値観や考え方について理解が深まります。「なぜそう考えるのか」「どんな経験が影響しているのか」といった背景まで知ることで、相手への理解が一層深まっていきます。
長い夫婦・家族生活において、衝突や問題は必ず起きます。大切なのは、衝突や問題を起こさないことではありません。問題が起きてもお互いが納得できる結論に到達できることです。問題が起きても解決に向かえるコミュニケーションです。
参考ページ:家族ライフサイクルと夫婦の危機
意見の違いがあっても、お互いを尊重しながら話し合える関係性を築いていきます。違いを認め合い、共に解決策を見出していく経験が夫婦関係を育んでいきます。
参考リンク:夫婦関係を育むコミュニケーション
「お金の管理」「休日の過ごし方」「仕事と家庭のバランス」など、実際の生活で直面する場面について、具体的に話し合います。予想される課題にも、前もって対処方法を考えることができます。
カウンセリングでは、カウンセラーが客観的な立場でお二人の対話をサポートします。
たとえば、「子育てについて」話し合う際。一方が「できるだけ早く子どもが欲しい」と考え、もう一方は「まだ具体的に考えられない」と感じているケース。このような価値観の違いも、丁寧な対話を重ねることで、お互いが納得できる方向性を見出すことができます。
パートナーに直接は言いにくいことでも、カウンセラーがいることで話しやすくなります。また、カウンセラーを通すことで、相手の意見も受け入れやすくなるものです。
人生の大切な節目である結婚。そのスタートラインに立つお二人を豊富な経験と専門的な知識で支援いたします。
カウンセラーは、公認心理師・ブリーフセラピスト・家族相談士の資格を取得しています。家族療法とブリーフセラピー(短期療法)は、人と人との相互作用、すなわちコミュニケーションの変化を通じて問題解決を図るカウンセリングです。お二人に最適な支援を提供いたします。
1回のセッションは90分。急かすことなく、お二人の気持ちに寄り添いながら進めていきます。カウンセリングの回数は、お二人の状況や目標に応じて柔軟に設定できます。もちろんお一人での相談(60分または90分)も承っております。
カウンセリングルームは、プライバシー保護と安全性確保の両立を目指しています。初めての方でも安心してご利用いただける環境と雰囲気づくりを心がけています。
参考リンク:プライバシー保護と安全性確立の両立
「言いたいことが上手く伝えられない」「相手の本当の気持ちがわからない」といった悩みにも、専門的な対話の手法を用いてサポートいたします。回を重ねるごとに、お二人のコミュニケーションがより豊かになっていくことを実感していただけます。
結婚前カウンセリングは、以下のような流れで進めていきます。
※ 詳しい流れは「カウンセリングの流れ」ページをご覧ください。
参考リンク:カウンセリングの流れ
カウンセリングという言葉に抵抗を感じる方は少なくありません。「将来のために、専門家に相談してみない?」といったやわらかな言葉で提案してみてください。それもむずかしければ、まずはお一人でお越し下さい。具体的な提案ができると思います。
一般的には3〜6回程度で充実した準備ができます。ただし、これはあくまで目安です。お二人の状況や目標に応じて、柔軟に回数を設定することができます。
ご安心ください。カウンセラーが丁寧に質問を投げかけながら、お二人の対話をサポートいたします。最初は日常的な話題から始めて、徐々により深いテーマについても話せるようになっていきます。無理のないペースで進めていきましょう。
はい。状況に応じて個別面談の時間を設けることも可能です。ただし、基本的には二人で話し合うことを大切にしています。カウンセラーが仲立ちとなることで、普段は伝えにくいことも、建設的な形で共有できるようになっていきます。
特別な準備は必要ありません。お二人の今の気持ちや考えをお持ちいただければ十分です。カウンセリング中に必要な資料などは、こちらでご用意いたします。