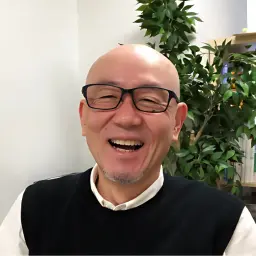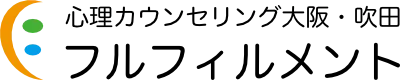人との関係において、いつも似たような問題が繰り返されると感じることはありませんか? 例えば以下のようなことです。
このような対人関係のパターンは、前の投稿で紹介したアタッチメントのスタイルと深く関係しています。
幼少期に養育者との関係によって形成されるアタッチメントは、その人の「人間関係の基本的な枠組み」を形作ると言われています。その枠組みは、生涯にわたって対人関係などに影響を与えます。
参考ページ:アタッチメント(1):自信が育つ土台
アタッチメントスタイルは年を重ねるほど強固なものになっていきますが、経験や人との出会い、環境の変化を通じて、変わりうるものです。
この投稿では、アタッチメントスタイルが人間関係に与える影響と、アタッチメントスタイルを変えていくための方法について考えていきます。
大人のアタッチメントスタイル
幼少期に形成されたアタッチメントは大人になっても影響を及ぼします。どのような影響が見られるか、アタッチメントの4つの型それぞれについて紹介します。
安定型
安定型のアタッチメントスタイルを持つ人は、対人関係において適度な距離感を保ちながらも、他者と親密な関係を築くことができます。自分の感情を素直に表現し、適切に他者を頼ることができるため、安定した人間関係を築きやすい傾向があります。
特徴
- 人と親密になることが容易
- 適切に他者を頼ることができる
- 感情のコントロールが比較的安定している
- 自分と他者の境界を適切に保つことができる
背景と影響
幼少期に養育者が一貫して温かく、適切に応答してくれた場合、「自分は愛される存在であり、他者は信頼できる」という前提が形成されます。そのため、大人になってからも人間関係において安心感を持ちやすく、対人関係における柔軟性が高くなります。
回避型
回避型のアタッチメントスタイルを持つ人は、親密な関係を避ける傾向があります。特に、感情的なやり取りや依存関係を負担に感じやすく、意識的または無意識のうちに他者との距離を取ろうとします。
特徴
- 感情をあまり表に出さない
- 他者からのサポートを受け入れにくい
- 自立を強く求め、依存することを避ける
- 対人関係においてクールでドライな印象を持たれやすい
背景と影響
幼少期に養育者が一貫して関心を示さなかったり、過度に厳しかったりした場合、子どもは「自分の感情を出しても意味がない」「他者を頼るのは危険だ」と学習します。その結果、大人になっても親密な関係を避ける傾向が続くことがあります。
アンビバレント型
アンビバレント型のアタッチメントスタイルを持つ人は、親密な関係を強く求める一方で、不安も強く抱えています。「相手に拒絶されるのではないか」「愛されていないのではないか」といった恐れを持ちやすく、人間関係において感情の波が大きくなりがちです。
特徴
- 相手の反応に過敏になりやすい
- 過剰に愛情や承認を求める
- 相手の些細な変化に強い不安を感じる
- 親密な関係を求めるが、不安から衝突を招きやすい
背景と影響
幼少期に養育者の対応が一貫しておらず、不安定な愛情を経験した場合、「愛情は保証されない」「見捨てられるかもしれない」という不安を抱くようになります。その結果、大人になっても相手の愛情を常に確認しようとし、依存的になりやすい傾向があります。
無秩序型(回避と不安の両方を持つ)
無秩序型のアタッチメントスタイルを持つ人は、親密な関係を求めながらも、同時に相手に対する恐れや疑念を抱いています。そのため、対人関係において一貫性のない行動をとりやすく、安定した関係を築くことが難しくなりがちです。
特徴
- 近づきたいのに、距離を取ろうとする
- 人を信頼したいが、同時に警戒心を抱く
- 感情のコントロールが難しく、対人関係が不安定になりやすい
- 相手に依存しつつも、拒絶的な態度を取ることがある
背景と影響
幼少期に養育者からの虐待やネグレクトを経験した場合、「愛情と恐怖が同時に存在する」という複雑な感情を抱くことになります。その結果、大人になっても人間関係において安定した関わり方がむずかしく、相手に近づこうとしながらも、突き放すような行動をとることがあります。
アタッチメントスタイルは変えられる
これらのアタッチメントスタイルは、幼少期に形成されるものですが、一生変わらないものではありません。信頼できる人との関係を築いたり、新しい経験を重ねたりすることで変わりうるものです。
アタッチメントが変化するとき
アタッチメントスタイルは固定されたものではなく、出会いや経験によって変化することがあります。以下のような状況がアタッチメントスタイルの変化を促すことが知られています。
一つずつ説明していきます。
信頼できる人との出会い
安定した人間関係の中で「受け入れられている」「信頼できる」という感覚を得ることは、アタッチメントの変化に重要な役割を果たします。例えば、職場やコミュニティなどで安心・安全な関係を築くことです。
このような関係は安全基地として機能し、過去のアタッチメントスタイルを見直す機会を与えてくれます。幼少期に養育者が安全な基地となることで、安定型のアタッチメントが形成されるのと同様です。
良好な恋愛・夫婦関係
恋愛や結婚などのパートナーシップも、アタッチメントの変化に大きな影響を与えます。安定した関係の中で、互いに信頼し合い、適切にサポートし合うことで、「人は信頼できる」「愛情は安定している」という新たな認識が生まれます。
安定した関係は、パートナーが安全基地として機能することを意味します。これによって、アタッチメントスタイルが安定型に変化することが期待できます。
ライフイベントの影響
人生の中での大きな出来事(出産、育児、転職、病気など)を経験したときに、アタッチメントスタイルが変化することがあります。
こうした状況では、過去のパターンを維持するよりも、新しい行動を取る必要が生じるため、結果的にアタッチメントスタイルの変化を促すことがあります。
困難な状況の中での変化
ときには、「それどころじゃない」と思うほどの困難な状況に直面することで、これまでのアタッチメントが変わることもあります。
他者に援助を求めざるを得ない状況になり、思い切って援助を求めてみると、周囲の人たちから大きなサポートを得る経験をして、認識が変わるような体験です。ある。
自己理解を深める
自分のアタッチメントスタイルの理解を深めることで、自分自身を客観的に見る視点を持てるようになり、安定に向かいやすくなります。
カウンセリングは最初の安全基地
アタッチメントスタイルの変化には安全基地が大きな役割を果たします。しかし、現実の人間関係では、誰もが常に安定した関係を提供できるわけではありません。
カウンセリングは安全基地として有力な選択肢の一つです。日常生活で関わりのないカウンセラーの方が安心して自己開示できること、守秘義務によって話した内容が守られることなどが、その理由としてあげられます。
参考ページ:ジョハリの窓をわかりやすく︰他者を通じて自己理解を深める
カウンセリングでは、自分の考えや感情を自由に表現できる機会が確保されます。また、どのような感情を抱えていても、批判や評価をされることなく受け止められます。
そのような環境の中で、自己開示とフィードバックを重ねること自体がアタッチメントスタイルの変化を促します。同時に気づきを促し自己理解が深まります。気づきが更に変化を促します。
- 数井みゆき (編集), 遠藤利彦 (編集) 2005 アタッチメント:生涯にわたる絆 ミネルヴァ書房
- 遠藤利彦 (著, 編) 2021 入門 アタッチメント理論 臨床・実践への架け橋 日本評論社
- 遠藤利彦 (監修) 2022 アタッチメントがわかる本 「愛着」が心の力を育む 講談社