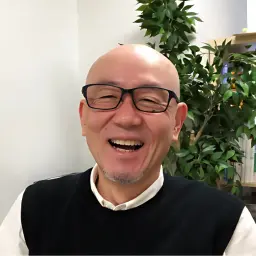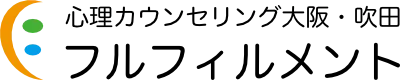「堂々巡り」とは、仏教における祈願のために仏堂や本尊、仏像の周りを何度も回る儀式のことです。そこから、絶えず動いているが同じ場所を巡っているだけで、前進・進行・打開しない状態を意味する表現として使われるようになりました。
堂々巡りに陥ると、何度考えても結論や解決策が見つからず、頭の中がネガティブの渦に飲み込まれるかのようになり、前に進めなくなってしまいます。失敗したことを何度も思い出して「もうダメだ…」と落ち込んでしまったり、「これしかない」と決めつけて新しいアイデアを試せなくなったりするのがその一例です。
この投稿では、クライエントさんが堂々巡りから抜け出すために、カウンセラーとしての私がどのような働きかけを行っているかをご紹介します。
堂々巡りの原因

堂々巡りに陥る原因として最初に挙げられるのは、考え方の偏りです。
人は考え方や行動の一定の型を持っています。何事もきっちりしたい人がいれば、大切なことだけきっちりやって、後は大ざっぱで良いという人もいます。
前者の人は、これまでの人生において、何事もきっちりやることで周囲とうまくやれる経験が多かったから、または、それを求められる環境にいる経験が長かったから、その型が習慣になったのかもしれません。
後者の人は、大切なこと以外は60点で十分という環境で過ごしてきたから、または、やるべきことが多すぎて、すべてをきっちりやるのは困難な環境にいる経験が長かったから、その型ができたのかもしれません。
どちらが良いとは一概に言えません。前者の人が後者の環境に置かれると、または、後者の人が前者の環境に置かれると、うまくいかなくて堂々巡りに陥るかもしれません。
余裕があるときは、他者からアドバイスを得て、他の型を採用する柔軟性を持ちやすくなります。しかし、ストレスが大きいときは、柔軟性を持つのがむずかしくなります。
考え方の偏り
繰り返しになりますが、人は自分自身の考え方や行動の型を持っています。これは、これまでの人生で置かれた状況にうまく対応するために身につけたものです。その型がうまく機能しない状況で、その型にこだわると、がんばればがんばるほど袋小路に迷い込んでしまうことがあります。
例えば、スピードを求められる状況で過度に丁寧さにこだわったり、逆に高い精度や慎重さを求められる状況でスピードを重視してしまったりするケースが考えられます。
認知行動療法では、これを「認知の偏り」と呼びます。認知の偏りには、「白黒思考」「べき思考」「極端な一般化」「個人化(うまくいかないことを自分の責任にする)」などがあります。
自分をつらくさせる認知の偏りに向き合い、柔軟な考えや行動を習慣にするサポートは、カウンセリングの主要な役割です。
参照ページ:認知行動療法
ストレスがたまっているとき
クライエントさんのお話を伺っていると、多くの方が自分自身の「認知の偏り」を認識されています。自分を客観的に見る視点を持っています。認知行動療法が世間に広く知られるようになり、情報を得る機会が増えているからだと思います。
しかし、ストレスがたまっているときは、自分を客観的に見るのがむずかしくなります。
普段は自分を客観視できる人でも、ストレス度が高いときは自分のことを客観的に見るのがむずかしくなるものです。認知の偏りを指摘すると、「あっ、わかっているのに、やってしまった」と反応されるのはめずらしくありません。
ストレスがたまっているときは、新しい選択がむずかしくなります。
人には知らないものを避けようとする傾向があります。いつも通りにするのが安心だからです。ストレスがたまるとその傾向がより強くなります。
DV・モラハラ被害者が加害者から離れるのがむずかしい理由も、不透明な未来を避けたい気持ちが働くからです。逃げた後を見通せない不安な未来より、苦痛でも予測できる現在を選択してしまいます。
大きなストレスは気づきますが、日々の小さなストレスは気づきにくいものです。
いちいち意識していたら前に進みません。イヤなことを忘れるのは心の健康を保つ機能でもあります。しかし、ストレスを感じる出来事を忘れても、気づかないうちにダメージが蓄積していることがあります。
また、ネガティブな出来事だけではなく、昇進や進学などのポジティブな出来事もストレスとして経験されることがあります。ネガティブであれ、ポジティブであれ、変化は負荷になるからです。
参照ページ:【ストレスと上手くつき合う】そもそもストレスとは何なのか
情報が足りない
情報不足によって判断が止まってしまうことがあります。「この方法で本当に合っているのか分からない」と迷って、前に進めなくなることがあります。
カウンセラーとして経験することの一つに「人は不確かな状況に弱い」という実感があります。
「どうすれば良いのかわからない」というクライエントさんのお話を聞いていると、何もやっていないわけではなく、今やっていることに確信を持てなくて、進めることに躊躇していることがあります。
その今やっていることが心理学的に理に適っているケースが少なくありません。
「心理学的にも理に適った選択をされていますし、私が同じ立場になっても同じ行動をしていると思います」とお伝えすると、「今やっていることが間違いではないとわかって安心しました」とスッキリした表情でお帰りになります。
迷ったときに相談できる安全な人や場所の存在は、とても意味があることだと実感する機会です。
その他
- 不安や恐怖:失敗が怖くて、同じ考えの中にとどまり堂々巡りに陥る。
- 自信がない:行動の一歩を踏み出せず、同じ考えの中にとどまり堂々巡りに陥る。
- 過去の失敗:過去の失敗を引きずり、同じ考えの中にとどまり堂々巡りに陥る。
- 周囲の影響:他人の期待や評価に過度に左右され、同じ考えの中にとどまり堂々巡りに陥る。
堂々巡りから抜け出す方法

堂々巡りから抜け出すための第一歩は「視点を変える」ことです。
堂々巡りに陥っている状態は、陸上選手がゴールのないトラックの周回を重ねているようなものです。陸上競技なら決められた周回を走りきればゴールです。堂々巡りの場合、何周走ってもトラックの中にゴールはありません。トラックの外に出なければなりません。
トラックの外に出るには、視点を変える必要があります。視点を変える方法をいくつか紹介します。
他の人の考え方を想像する
他人の視点を取り入れる方法です。私の場合であれば、「スーパーバイザーの○○先生に相談したら、どのようにアドバイスするだろうか」「同じ研修を受けている○○さんなら、どのように考えるだろう」といった要領です。
自分に以下のような質問を投げかけます。
他人の視点を取り入れると、見逃していた情報や別の発想に気づきやすくなります。以下のステップを加えると、より思考が働くことが期待できます。
- 紙やノートに「○○さんならどう考える?」と書く。
- その人がなぜそう考えるか、その背景や思考を想像する。
紙に書き出すなどして、頭の中にあるものを外に出すのは効果的です。自分の思考を少し距離を置いてみることで、客観的な視点を持ちやすくなります。また、考えを言語化する過程で新たな気づきを得られることもよくあります。
過去や未来の自分から現在を見る
メジャーリーガーのダルビッシュ有投手のエピソードが有名です。
ダルビッシュ有投手が20才の2006年のことです。
ある試合で大量失点してKOされてしまいました。その夜、眠れずに将来のことを考えていました。そのとき、以下のような考えに至ったそうです。
「これまでの20年はあっという間だった」
「40才までの20年もあっという間だろう」
「このまま40才になった自分は、大した選手になれずに引退して、引退後は仕事もないだろう」
「その40年後の自分の前に神様が現れて、『1度だけチャンスをやろう。20才に戻してあげよう』と言われて今ここにいるのが自分だと考えよう」
「40才になって人生を失敗したところから、神様のおかげで人生をやり直せる機会を得たと思い込んでやっていこう」
20才の頃に、そのような考えに至れることがスゴいと感じる私です。20才の頃の私は…正直、あまり考えたくありません。
それはともかくとして、「過去や未来の自分から今の自分にアドバイスするとしたら?」の問いは新たな視点をもたらしてくれるはずです。
このような問いをかけることによって、先延ばしにしていたことに着手するかもしれません。今までやっていたことをやめる勇気が出るかもしれません。問題と思っていたけれど、大した問題ではないと気づくことがあるかもしれません。
距離を置いて見る
頭の中にあるものを紙に書くのは、自分の考えを距離を置いて見ることにつながります。客観的な視点を得て、見えなかったものが見えて、気づきを得て、堂々巡りから抜け出すきっかけを得ることができます。
逆にもっと近づくことで、見えなかったものが見えて、バラバラに見えることが、実はつながっていることに気づくかもしれません。何でつながっているのか見える化もしれません。
職場の人間関係で悩んでいるクライエントさんにこのアドバイスをしたことがあります。そのクライエントさんは、「自分と、同じ部署の人たちと、自分がいるフロアを、3階から見下ろしているイメージを思い浮かべると、何かどうでも良くなりました」とおっしゃいました。
状況が変わったらどうなるかを考える
状況が変われば、出来事の意味も変わります。商売繁盛で「忙しい」なら笑顔で訴えているかもしれません。睡眠時間を削って働いているなら疲労困憊でメンタルヘルスの問題を心配する必要があるかもしれません。
状況が変わったらどうなるかを考えてみることで、新しい視点を得られるかもしれません。
自己啓発で有名なデール・カーネギーの著書『道は開ける』には、最悪の事態を乗り切る方法として以下の3つのステップが書かれてあります。読んだのはかなり前のことですが、今でも救われる機会があります。
- 起こりうる最悪の事態を具体的に想定する
- 最悪の事態を受け入れると覚悟する
- 今できることに集中する
最悪の事態を具体的に記述してみると、不安のサイズが現実的な大きさになります。気持ちを切り替えて前に進みやすくなります。
ちなみに、回避すればするほど不安が大きくなるのが不安症のメカニズムです。認知行動療法の曝露法(エクスポージャー法)は、あえて不安に自分を無防備に晒す体験を積み重ねる技法です。
変えられることと変えられないことを区別する
カウンセラーがクライエントさんと一緒に、変えられないことを一生懸命変えようとして、それに気づかず悩んでいることがあります。
経験を積んだカウンセラーが戦略的にクライエントさんと一緒に悩むこともありますが、初級のカウンセラーの場合、クライエントさんの感情に巻き込まれて一緒に悩んでいることがあります。
何を言いたいかというと、変えられないことを変えようとして苦しむのは、カウンセラーとしての訓練を積んだ人でも陥ることがあるということです。ニーバーの祈りが語り継がれているのは、誰もがいつでもその状態に陥ることを示していると思います。
ニーバーの祈り
神よ、変えられるものを変える勇気を、
ニーバーの祈り – Wikipedia
変えられないものを受け入れる冷静さを、
そして両者を識別する知恵を与えたまえ
堂々巡りに陥っているとき、「変えられることと変えられないことを区別しよう」と自分に語りかけることは、膠着状態から抜け出すきっかけになり得ます。
「他人と過去は変えられない」と言いますが、必ずしもそうではありません。自分が変わること、自分を変えることによって、他人が変わることがあります。過去の出来事自体は変わりませんが、過去の意味を変えることはできます。
参考ページ:過去と他人は本当に変えられないのか?
長くなりましたが、以上でこの投稿を終わりとします。みなさまが堂々巡りから抜け出すきっかけになればうれしいです。この情報だけではむずかしい場合は、カウンセリングの利用をご検討下さい。言葉だけでは伝えきれないサポートを提供できます。