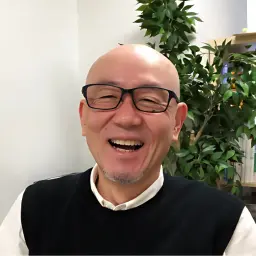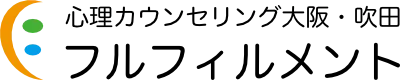多くの人が経験する「先延ばし」
それは、単なる怠けや時間の使い方の問題ではなく、私たちの心の奥にある「自分への厳しさ」や「完璧でありたい気持ち」と深く結びついていることがあります。
そんな経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。私もその一人です。
今回ご紹介するのは、「先延ばし」のクセを改善したいライターさんのカウンセリング事例です。
「書くべきだと分かっていても手が進まない」という先延ばしの背景にある、自尊心の揺らぎや完璧主義との葛藤。そうした心の動きを掘り下げていった面接です。
ブリーフセラピーでは通常、問題や原因を掘り下げることはしません。問題を維持している「悪循環」を断ち切って、問題のない状態(解決像)を広げていくサポートを行います。しかし、クライエントさんが希望される場合は話は別です。ご要望に応えることが優先されます。
このケースは、一般的なブリーフセラピーとは異なるアプローチの事例です。しかし、クライエントさんの役に立つなら何でもありという柔軟さも、ブリーフセラピーの特徴の一つです。そのような視点でご覧いただければと思います。
なお、事例の紹介にあたって、ご本人の許可を得ており、個人が特定されないように内容を改変しております。
なぜ先延ばしをしてしまうのか
なぜ私たちは、「やった方がいい」と分かっていながら、先延ばしをしてしまうのでしょうか。
「面倒くさい」「気が乗らない」といった感情の背景には、まだ言葉になっていない別の感情が潜んでいることがあります。つまり、その奥にある感情が「面倒くさい」「気が乗らない」という形で表現されているのです。
今回ご紹介する事例では、次のような心の動きが見えてきました。
こうした複数の要因が絡み合い、「先延ばし」という行動を形づくっていました。
カウンセリング事例
クライエントさんは、30代の女性です。民間企業に勤めながら、副業としてフリーランスのライターをされています。将来的には本業にしたいという目標を持っていらっしゃいます。
クライエントの訴え
カウンセラー:今回のご相談について聞かせてください。
クライエント:ライターの仕事についてなんですが、最近、どうしても手が止まってしまっていて……。記事のアイデアを出したり、たたき台を作ったりするところまではできるんです。でも、そのあとの「内容のチェック」になると、なぜか進められなくなってしまうんです。
カウンセラー:たたき台までは順調に進められているのですね。そのあと手が止まってしまうとのことですが、その状態について、詳しく聞かせてください。
クライエント:そうですね……チェックしなきゃいけないのはわかっているし、自分のためにやらなきゃいけないことなんですけど、なぜか向き合えなくて……。パソコンの前に座っても、別のことを始めたりして、先延ばしばかりしてしまいます。何というか、「うんざり」した気持ちになってしまうんです。
カウンセラー:「うんざり」する感覚なのですね。それは、例えば量の多さや手間が原因でしょうか。それとも、他に理由があるように感じますか。
クライエント:うーん……量が多いとか、そういう問題ではない気がします。なんでこんなに嫌になるのか、自分でもよくわからなくて……。やったほうがいいのに、なんだか避けたくなってしまうんです。
カウンセラー:今回、はじめてカウンセリングに来てくださったとのことですが、何がどのようになれば、ここに来て良かったなあと思えそうですか。
クライエント:自分でもモヤモヤしていて、まずはその理由を知りたいという気持ちが強いです。どのように対処するかも大事なんですけど、今は、このモヤモヤを明確にしてスッキリしたい気持ちが強いです。
解説
クライエントは、副業としてライター活動を続けながら、将来的には本業にしたいという明確な目標を持っていました。自身の認知度を高めるために、今は記事を多く発信していく必要があると考えており、様々な取り組みによって、効率的にたたき台までは作成できているとのことでした。
しかし、そのあとの「内容チェック」の段階で手が止まり、「うんざり」した気持ちになってしまうという状態が続いていました。自分のためにやらなければならないことだと理解していても、向き合うことに抵抗を感じ、無意識に先延ばししてしまいます。
クライエントはこの状態に強いモヤモヤを抱えており、「解決策」よりもまずはその感情の正体を知りたいと望んでいました。
カウンセラーは、作業へのストレスがどこから生じているのか、まずはその感情の背景を丁寧に探ることから対話を始めました。
感情の解像度を高める
カウンセラーはクライエントさんに、「うんざり」や「モヤモヤ」を、具体的な言葉で表現するように促していきました。私はこの営みを「感情の解像度を高める」と表現しています。例を以下にあげます。
| 解像度が低い | 解像度が高い |
| なんかモヤモヤする | 母親に本音を言いたいけれど、言ったら関係が悪くなりそうで怖い |
| イライラする | 自分の意見が聞いてもらえないと感じて、無力感と怒りが入り交じっている |
解像度が高くなると、整理しやすくなります。問題と思っていたことが、実は問題ではなかったと気づくことがあります。問題が明確になるだけで、悩みが小さくなることもあります。

深掘りと気づき
クライエント:そうですね…。こうして問われてみると、記事の「量」自体は大きな要因ではないように思います。すぐに思いつくのは、PCのディスプレイを見続けることのしんどさです。目が悪いので。ただ、それは些末なことで、主たる原因ではないと思います。
カウンセラー:なるほど。他に何か感じることがありますか。例えば、作業をしながら、もしくは作業をする前に、心の中でつぶやいたりしていることはありますか。
クライエント:作業をしているときですか…。そうですね…。チェック作業中に「ちょっと違う」とか「もっと良い表現があるはず」と考える一方で、しっくりくる言葉を自分の中から引き出せないことがしばしばあります。そのようなとき、モヤモヤというか、イライラというか、すごくストレスを感じています。
カウンセラー:言葉が出てこないことへのストレスですね。それはどのような気持ちにつながりますか。
クライエント:なんというか、「自分の能力の低さ」に直面しているような気持ちになります。あと、早く作業を進められないのも、結局自分の能力が低いせいだと感じてしまって…。この年まで生産性の低い生き方をしてきたんじゃないかという虚しさや後悔に包まれたり、同窓会やSNSで聞いた学生時代の同期の活躍を思い出して、自分と比較して苦しくなることもあります。
カウンセラー:ご自身の能力や過去の選択に対して、とても厳しい評価をされているのですね。そして、その「自尊心が傷つく経験」を避けたいという気持ちが、作業から目を背けさせているのかもしれません。完璧主義の傾向は感じますか。
クライエント:完璧主義も関わっていそうです。「完璧なものができない=能力がない」って、どこかで思っている気がします。
解説
対話を進める中で、クライエントさんの「モヤモヤ」の根底にある感情が少しずつ明らかになってきました。作業量の多さではない。PCの画面を見続けることによる身体的な負担があるものの、それは些末な問題である。より大きな負担となっていたのは、言葉が出てこない時の焦りや無力感でした。
注目すべきは、「言葉が出てこない」「作業が進まない」といった出来事を、即座に「自分の能力の低さ」と結びつけてしまう思考のパターンです。これは認知行動療法でいうところの「過度な一般化」や「拡大解釈」にあたります。
過度な一般化:1つの失敗やイヤな出来事があると、「いつも〜だ」「すべて〜だ」のように一事が万事と考える。
拡大解釈:自分の欠点や失敗を過大に考え、長所や成功を過小評価する。逆に他人の成功を過大に評価し、他人の欠点を見逃す。
さらに、このような自己評価は過去の後悔や他者との比較とも結びつき、より深い自尊心の傷つきを引き起こしていました。
また、「完璧なものができなければ、自分には能力がない」といった思考は、「全か無か思考(白黒思考)」として知られています。これは、少しでも不完全な部分があると、自分全体の価値を否定してしまう思考パターンであり、着手する意欲をさらに低下させる原因となります。
全か無か思考(白黒思考):ものごとを白か黒かのどちらかで考える。少しでもミスがあれば、完全な失敗と考えてしまう。
問題の明確化
問題(悪循環)を共有します。
悪循環を描く
カウンセラー:お話を伺っていると、2つのパターンがあるようです。一つ目は、「(以下の囲みの内容)ですね」
自尊心が傷つくのを避けたい
→ 作業を先延ばしする
→ でも結局やらなければならず、さらに自分を責める
→ ますます傷つきを避けたくなる
→ 以上を繰り返す
カウンセラー:もう一つは、「(以下の内容)ですね」
完璧なものを作りたい
→ でも完璧にできない
→ 自分には能力がないと感じる
→ ますます完璧を求める
→ 以上を繰り返す
クライエント:ああ、そうです。まさにそれです。言葉にしてもらうと、すごく腑に落ちます。特に一つ目は、まさに今の私そのものですね。作業に向き合うと「またうまくいかないんじゃないか」って思って、それで避けてしまう。でも避ければ避けるほど、「やっぱり私はダメなんだ」って思いが強くなって…。
カウンセラー:これまでは「うんざり」「モヤモヤ」としか表現できなかった気持ちが、こうして具体的なパターンとして見えてきましたね。
クライエント:今まではただ漠然と嫌な気持ちになっていたのが、こんなふうに明確な言葉で表現されると、本当にスッキリしました。何が起こっているのかが分かると、こんなに違うものなんですね。
カウンセラー:今日はモヤモヤを明確にしたいとおっしゃっていましたが、明確になりましたか?
クライエント:はい、とても明確になりました。
カウンセラー:「言葉が出てこない」「作業が進まない」といった出来事で、全人格を否定的に見てしまう傾向があるみたいですね。もっとも、この傾向は私にもありますし、同じ傾向がある人は少なくないと思います。
クライエント:ああ、確かにそうですね。部分的なことで全体を決めつけてしまっているかもしれません。
カウンセラー:「完璧なものができなければ意味がない」という考え方も、先ほどお話しされていましたね。「完璧でなくても良い」「まずは完了させる」ことを優先するという選択肢もあるかもしれません。
クライエント:そうですね。完璧主義から少し距離を置いてみることも大切かもしれません。
解説
「うんざり」「モヤモヤ」としか表現できなかった漠然とした感情が、明確な言葉で表現されて、感情の解像度が向上しました。今回の目標である「モヤモヤを明確にしてスッキリしたい」を達成することができました。
おわりに
今回は、感情の解像度を高めることで心が整理されたカウンセリングをご紹介しました。
解決には様々な形があり、これも解決の一つの形です。おそらくクライエントさんは、ここから更に自己解決に向かわれると思います。当カウンセリングルームは、あなたにとっての解決にたどり着けるよう、サポートを提供します。
カウンセリングは心の病を抱えている人が受けるものというイメージがあるかもしれません。必ずしもそうではないことを示す事例でもあります。当カウンセリングルームでは、今回のようなケースや、人間関係、夫婦・家族関係など、日常生活における困りごとの相談を多く受けています。関心のある方は一度お問い合わせ下さい。